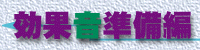 |
DD-1000、MDを使った仕込み。
やっぱり6mmが便利。
オールデジタルより、
デジタルとアナログの併用がgood!。 |
 |
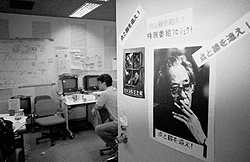 いよいよ効果音の仕込み(準備)です。編集されたVTRをもとに、音楽やSE(効果音)のプランニングを再構築します。 いよいよ効果音の仕込み(準備)です。編集されたVTRをもとに、音楽やSE(効果音)のプランニングを再構築します。
「なぜ今更再構築?台本に忠実に音を付けたらいいのに」
と思うでしょう。ですが、一般の生産業と違って設計図どおりにVTRは仕上がって来ません。
撮影現場や編集現場での思いつきや思いこみが、台本と違った設定やセリフに姿を変えさえます。もちろん、良いと思われる発想を作品の中に織り込んで行くわけですが・・。そうやって出来たVTRを基に音楽やSEのプランニングを再構築していくことになるわけです。
まぁ、前置きはこれくらいにして・・、まずはVTRを見まくります。とにかく見る!四の五の言わずに見るんです。そして、ワンカットづつのラップをノートに書いていきます。編集された映像をバラバラにして、シーンの内容や編集意図を把握していきます。一つのシーンに、音がどんなタイミングやバランスで入るともっとも効果的なのか?いっそ音を消してしまって、何もない方が効果的になるか?などを改めて検討していくためです。
今回はVTRを受け取ってから放送まで2週間しかありません。時間に余裕が無いので必要最小限の効果音を仕込むので手一杯かもしれません。
 そこで今回、効果音を効率よく仕込むために、AKAIのDD-1000,MOディスクレコーダー(以下DD-1000)を使うことにしました。どういったところが便利かと言うとVTRのタイムコードと同期できる点です。タイムコードって言われても分からない人は“番組の開始から終了までの時間”がVTRの中に入っているとでも思って下さい。流出物のビデオの画面の上か下の方に【00:10:15:20】とか出てますよね。あれです(爆)。そのタイムコード(TCR)の時間とDD-1000が仲良く手を繋いで動いてくれるのです。 そこで今回、効果音を効率よく仕込むために、AKAIのDD-1000,MOディスクレコーダー(以下DD-1000)を使うことにしました。どういったところが便利かと言うとVTRのタイムコードと同期できる点です。タイムコードって言われても分からない人は“番組の開始から終了までの時間”がVTRの中に入っているとでも思って下さい。流出物のビデオの画面の上か下の方に【00:10:15:20】とか出てますよね。あれです(爆)。そのタイムコード(TCR)の時間とDD-1000が仲良く手を繋いで動いてくれるのです。
たとえば、【チャンバラ】のキン、カキン、キーンと刀同士がぶつかるシーンがあるとします。通常はそのぶつかる音を一つずつ準備してMA(ダビング)ルームで一つずつ映像に合わせて付けていきます。なにげなくテレビでみなさんは見ているかもしれませんが、結構時間のかかる作業をしているのです。しかし、DD-1000を使うことで作業の時間短縮が出来るのです。
 刀がぶつかる音の一つ一つは準備しなくてはなりませんが、準備した音をDD-1000に録音し、10時00分01秒に“刀にぶつかる音-1”つづいて10時00分02秒に“刀にぶつかる音-2”つづいて10時00分03秒に“刀にぶつかる音-3”というふうにDD-1000に覚えさせると、VTRのその時間が来たらちゃんと“刀にぶつかる音-1”から“刀にぶつかる音-3”をつづけて出してくれるのです。そこで私は今回のドラマでこんな使い方をしました。 刀がぶつかる音の一つ一つは準備しなくてはなりませんが、準備した音をDD-1000に録音し、10時00分01秒に“刀にぶつかる音-1”つづいて10時00分02秒に“刀にぶつかる音-2”つづいて10時00分03秒に“刀にぶつかる音-3”というふうにDD-1000に覚えさせると、VTRのその時間が来たらちゃんと“刀にぶつかる音-1”から“刀にぶつかる音-3”をつづけて出してくれるのです。そこで私は今回のドラマでこんな使い方をしました。
番組の冒頭に主人公・新庄礼子(牧瀬里穂)がモノレール小倉駅のコンコースを歩くシーンがあります。映像は、主人公の方にカメラがレールを使ってローアングルで回り込んで近寄ったところを新庄礼子が通過するといったシーン。黒澤明監督の“羅生門”の木こりが山道を歩くシーンをパクッタかっこいいワンカットでした。しかし、音の方は一般の通行者の雑踏や野次馬達の会話がコンコースのドーム型の屋根に反響した、ただ“うるさい”といった音でした。新庄礼子の足音などもちろん聞こえません。目の前を通過したときやっとかすかに聞こえる程度です。そこで、そのワンカットの音をまるまるハメカエました。人々が行き交うコンコースのベースノイズは、先日録音してきた音を使いました。これで背景音はOK。
次に新庄礼子の足音です。録音ブースにハイヒールとコンクリート板を持ち込みVTRを見ながら歩こうとしました。が・・・、自分の足のサイズとハイヒールのサイズが合わなくて歩くことはもちろん履くことさえ出来ず断念。今度は手にハイヒールをはめてやってみたら、けっこういい音がしたので、VTRに合わせてやってみようと思いました。しかし、ここであることに気が付きました。
 【VTRを再生、DD-1000を録音、ブースに駆け込みマイクの前でハイヒールを手にはめてVTRを見たら次のシーン】になってしまいます(笑)。長めに前からVTRを再生してコンコースのシーンが来るのを待つのもばかばかしい。そこで、DD-1000を録音状態にしてブースに駆け込み今度は映像に合わせずに自分の間合いでハイヒールの音だけを録音しました。単純にハイヒールの音だけを録音した訳です。そしてその録音したハイヒールの音をDD-1000で一歩ずつに切り刻んで新庄礼子の歩く映像の一歩一歩の時間にハイヒールの音が出るようにDD-1000に覚えさせました。【02:03:10に右足、02:03:17に左足】といった具合にDD-1000を設定した訳です。20歩程度のワンカットだったのでそんなに苦労せず出来ました。 【VTRを再生、DD-1000を録音、ブースに駆け込みマイクの前でハイヒールを手にはめてVTRを見たら次のシーン】になってしまいます(笑)。長めに前からVTRを再生してコンコースのシーンが来るのを待つのもばかばかしい。そこで、DD-1000を録音状態にしてブースに駆け込み今度は映像に合わせずに自分の間合いでハイヒールの音だけを録音しました。単純にハイヒールの音だけを録音した訳です。そしてその録音したハイヒールの音をDD-1000で一歩ずつに切り刻んで新庄礼子の歩く映像の一歩一歩の時間にハイヒールの音が出るようにDD-1000に覚えさせました。【02:03:10に右足、02:03:17に左足】といった具合にDD-1000を設定した訳です。20歩程度のワンカットだったのでそんなに苦労せず出来ました。
設定が終わりコンコースのシーンの頭にVTRを巻き戻して見てみると一歩づつのバラバラだったハイヒールの音が見事に繋がって映像と同期しました。こうやってその他のシーンに出てくる“携帯電話,椅子に座る,本を開く”等の【きっかけ音】をDD-1000に録音し時間設定をしていきました。
しかし、またしても盲点がありました。DD-1000は長時間の録音が苦手だったのです。なぜかと言うと、DD-1000の録音媒体は650メガMOディスクのためサンプリング周波数44.1Khz(CDと同様の音質)で約30分しか録音出来ないのです。背景音となるベースノイズとかDD-1000に録音していたらたちまちパンクしてしまいます。パンクしても別のディスクに替えれば良いのですが、長いシーンの時とか途中で止めたくないし、機械に頼りすぎないためにもベースノイズといった長尺の音は6mmテープに仕込んでいきました。映像の動きに付けるキッカケ音は、DD-1000。映像に奥行きを付ける背景音は6mmで行いました。
さて、この『点と線を追え!』における効果音を創る上でのテーマと言いましょうか、いわゆるサウンドデザインのテーマですが、私自身が一番表現したかったのは、この作品の舞台にもなっている“北九州”のインダストリアルサウンドでした。
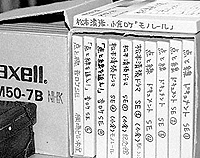 今回の作品は、ストーリー面で通常のドラマのようなクライマックス的な見せ場があるわけではありません。ただし映像的な表現は“野猿”井上たちスタッフ独特の世界が広がっています。「時に優しく、時に悲しい、時に厳しい」、松本清張が生きた北九州の映像。この世界を表現するには、“鉄の町”と呼ばれた工場地帯の音だと思いました。そして、このインダストリアルサウンドこそが、この作品のサウンドデザインにおけるテーマに相応しいと思いました。 今回の作品は、ストーリー面で通常のドラマのようなクライマックス的な見せ場があるわけではありません。ただし映像的な表現は“野猿”井上たちスタッフ独特の世界が広がっています。「時に優しく、時に悲しい、時に厳しい」、松本清張が生きた北九州の映像。この世界を表現するには、“鉄の町”と呼ばれた工場地帯の音だと思いました。そして、このインダストリアルサウンドこそが、この作品のサウンドデザインにおけるテーマに相応しいと思いました。
 では、そのインダストリアルサウンドをどのように創っていったか解説しましょう。 では、そのインダストリアルサウンドをどのように創っていったか解説しましょう。
効果音ライブラリーにある工場地帯の音、“ワイヤー切断”と“鍛冶屋の金槌”を二台の6mmに高速でダビングし、それぞれを超低速で再生したものを合わせてみました。“ワイヤー切断”の【ギュ〜ン】とした高音が【ギユワ〜ウオ〜ン】と低音の音に変化し、“鍛冶屋の金槌”の【キンキン】とした高音が【ガーンガーン】とした杭打ちのような音になりました。この二つを交互に来るように再生してみました。すると【ガーンギュワ〜ウオ〜ガーン】とすごい音になりました。そこにリバーブをあしらってやると、低音が効いた『鉄の町』的な音になりました。
しかし、これだけだとやや現実離れしているので“ゴミ処理場のトラックからゴミが落ちる音”と“溶鉱炉”の電子サイレンを足してやることにしました。これで、リアルな感じが出ている割に存在感のある工場地帯の音が出来ました。
作品の中には数カットしか出てこなかった工場地帯の映像が、こういった効果音を付けることで生き生きとしてきました。実際に放送された後のモニター報告の中で【工場の太い音が松本清張の生き様を表しているような気がした】といった意見があり、拘って創った甲斐があったと思いました。 |
|